お金の不安と子育て―将来の悩みを解決する具体的な方法

こんにちは、はるちゃんです。
今回の記事では「子育て世代のお金の不安」を大きなテーマに、お金の不安を具体的に解説しながら、解決のヒントをご紹介していきます。
実はお金の不安を解決するにはまず、「不安を具体的」に捉えることが大切です。特に「教育費はどれくらいかかるのか」「習い事をさせたいけれど家計は大丈夫か」「将来の生活資金まで備えられるのか」など、悩みの言語化が進めば手段が明確になり、スタートが切れるようになります。記事を読みながら、頭の中を整理していってくださいね。
Contents
1. 子育て世帯に多い「お金の不安」とは?
このブログも「お金不安 子育て」という検索の中で、辿り着いていただいたのではないでしょうか?皆さんが感じているお金の悩みを整理してみましょう。
1-1 教育費の捻出
文部科学省の「子供の学習費調査(令和3年度)」によると、公立小学校から大学まで進学した場合の教育費は1,000万円以上、私立の場合は2,000万円以上に達するといわれます。
特に大学入学時の費用は大きく、入学金・授業料・一人暮らしのための生活費まで含めると、家庭にとって大きな経済的負担となるタイミングです。
1-2 習い事の費用
スイミングやピアノ、サッカー、英会話などの習い事は、子どもの成長に役立つ一方で、月謝や発表会費用などが積み重なります。特に兄弟姉妹がいる場合、習い事の費用は倍増し、家計に大きな負担となります。
1-3 家計管理の課題
多くの家庭では家計簿をつけていますが、「赤字から抜け出せない」「貯金が思うようにできない」という声も少なくありません。原因は、固定費が高すぎる、教育費の見積もりが甘いなど、家庭ごとに異なります。
1-4 老後資金の準備
子育て中は子どもの教育費に意識が集中しがちですが、自分たち夫婦の老後資金も並行して準備する必要があります。住宅ローンが残っている場合、退職後に支払いを続けることになるケースもあり、将来の不安が増します。
2. 教育資金の真実―本当に2000万円必要?
2-1 進路によって大きく異なる教育費
教育費はどこを目指すのかで準備する金額は大きく異なります。
お子さんが都心の医学部を目指すとなれば住宅ローン並みの費用が必要になることも視野に入れないといけません。
具体的な費用例(4年間の総額)
- 国立大学(文系):約240万円
- 国立大学(理系):約260万円
- 私立大学(文系):約400万円
- 私立大学(理系):約550万円
- 私立大学(医学部):約2,000万円
私立か国立か、理系か文系か、都心か地方どの条件で教育資金を考えていくのかで全く準備するお金が変わることを理解しておいてください。
その上で大切なのは、親としてどこまでサポートしたいと思うかです。
まずは、情報を集めましょう。
2-2 奨学金や助成制度の活用も視野に入れる
奨学金制度は返済型だけでなく、給付型も増えています。支給対象の要件は、多くの場合「親の年収」に対して条件が決まっています。
大学で利用する奨学金であれば、高校生の時に申請をすることになり、高校時代のお子さんの学力(通知表)も奨学金を受け取ることができるかの一つの基準となります。
親として選択肢を知っておき、幅広い選択肢を持っておきましょう。
2-3 児童手当を教育費に充てる
児童手当を生活費に使わない。これだけで将来のお金の不安を大きく軽減できます。家族構成によって金額は異なりますが、小さな積み重ねでも、将来の入学費用に備えられます。
0歳から中学卒業まで児童手当をすべて貯蓄した場合、総額は約200万円になります。これだけで大学の入学金や初年度の学費をカバーできる計算です。
3. 習い事は必要なのか?費用対効果を考える
3-1 習い事費用の現実
ベネッセ教育総合研究所によれば、小学生の習い事にかかる平均費用は月1万円以上。ピアノや英語、スポーツなどを複数受講すれば、月2〜3万円に膨らむことも珍しくありません。
人気の習い事と月額費用の目安
- スイミング:6,000〜8,000円
- ピアノ:8,000〜12,000円
- 英会話:8,000〜15,000円
- サッカー・野球:5,000〜8,000円
- 塾(小学生):15,000〜25,000円
3-2 費用を抑える工夫
- 公共施設や地域センターが主催する低価格の講座を利用
- オンライン教室を活用
- 中古の教材や道具を利用
- 兄弟割引のある教室を選ぶ
習い事も多様化し、選択肢が増えたことで、習い事選びに迷っている家庭も多いと思います。
ただ、早期(3歳未満)の知育学習は将来的な学力に直接つながらないという見解も出てきています。
親のエゴになっていないか、「周りの子がやっているから」だけが理由になっていないか、そもそも習い事をする意味はあるのか?ここも大切にしてくださいね。
4. 家計簿が続かない理由と解決法
家計簿は不安解消の第一歩です。収入と支出を「見える化」することで、無駄を把握しやすくなります。
分かっていても続けられないのが現実ですが、家計簿にもステップがあります。自分に合ったステップで始めてみるのがおすすめです。
4-1 管理方法はアナログ派?デジタル派?
アナログは手書き家計簿、デジタル派はアプリを活用してください。どちらでも構わないという方は、アプリがおすすめです。家計簿アプリを使えば銀行口座やクレジットカードと自動連携でき、記録の手間が省けます。子育てで忙しい家庭にこそ、スマホアプリの導入は有効です。
4-2 始めから細かく分けない、支出は大きく3つでOK!
支出を「固定費」「変動費」「特別費」に分けると、改善点が明確になります。
- 固定費:住宅ローン、保険料、学費、通信費
- 変動費:食費、光熱費、日用品、交通費
- 特別費:旅行費、進学費用、冠婚葬祭
特に固定費を削減できると、家計が一気に改善しやすいです。保険の見直しや通信費の削減など、一度見直せば継続的に効果が得られます。
4-3 見える化したら誰かに見てもらう
家計が見える化できたら、夫でも友達でも、自分以外の誰かにまずは見てもらいましょう。近くの人には恥ずかしいと思う方は、自治体の無料「家計見直し相談会」を活用してもよいかもしれません。
このような家計の見直しは、一人で行うと見落としがちな部分もあります。客観的な視点からアドバイスを受けたい方は、専門家による無料相談もご活用ください。
大切なのは「自分の当たり前を疑う機会を作ること」です。
5. 老後資金の考え方―子育てと両立するコツ
老後2000万円問題と言われても、どうすればよいのか分からない人も多いかもしれませんね。
国はiDeCoやNISAを準備したことで、年金に頼らない自助努力を国民に求めています。
5-1 ライフプランを立てる
これまでも何度も出てきましたが、まずは老後にどのような状態を目指していきたいのかが重要です。月いくらで生活をしたいか——これによって準備方法も変わるでしょう。住みたい地域の物価水準も考慮しながら考えていくのがおすすめです。
老後の生活費の目安
- 夫婦二人の最低生活費:月23万円
- ゆとりある老後生活費:月37万円 (生命保険文化センター「令和4年度生活保障に関する調査」より)
5-2 教育費と老後資金の両立
子育て世代は「教育費」と「老後資金」を同時に考えなければなりません。iDeCoやNISAなどの制度を活用すれば、少額からでも老後資金を積み立てられます。
両立のコツ
- つみたてNISA:月1万円から始められる
- iDeCo:節税効果があり、教育費がかかる時期の税負担を軽減
- 教育費のピーク後に老後資金の積立額を増やす
その上で、どのような手段を使っていくのかは、専門家に一度相談していくのがよいと思います。
5-3 専門家に相談するメリット
ファイナンシャルプランナーに相談すれば、教育費・住宅ローン・老後資金を総合的に考えたアドバイスが得られます。特に地域に詳しい相談員は、自治体の助成制度も踏まえた提案をしてくれるので安心です。
6. まとめ―貯金だけでは解決しない現実と新しい道筋
正直にお話しします。子育て世帯の教育費・老後資金の問題は、節約や貯金だけでは解決が困難です。
なぜなら:
- 教育費は年々上昇している
- 給与収入だけでは限界がある
- 物価上昇で生活費も増加している
だからこそ、多くの賢い親が始めているのが「副業による収入の複数化」です。
副業を始めることで:
✓ 家計に余裕が生まれる
✓ 確定申告で節税効果を得られる
✓ 将来への不安が軽減される
✓ 子どもにも「稼ぐ力」を教えられる
私たちは、子育て世帯が無理なく始められる副業選びから、確定申告による節税サポートまで、一貫してお手伝いしています。
無料相談で解決できること
- 子育て世帯に最適な副業の見つけ方
- 副業収入を最大化する方法
- 確定申告を活用した具体的な節税方法
- 家計改善のための収入アップ戦略
子育て世帯の皆さんが「稼ぐ力」を身につけて、お金の不安から解放されるよう、お一人おひとりに寄り添ったサポートを心がけています。
お金の不安から解放されて、子育てを楽しみませんか?
\ 副業×節税で家計改善したい方 /
まずは無料相談でお話を聞かせてください
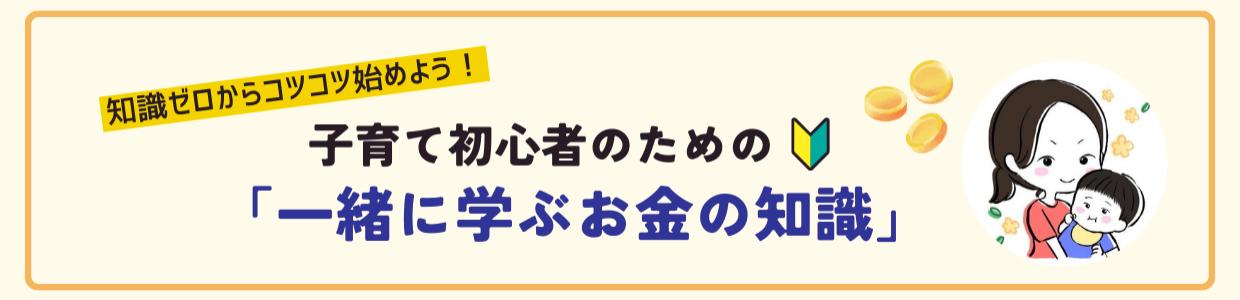
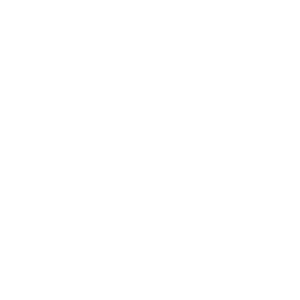
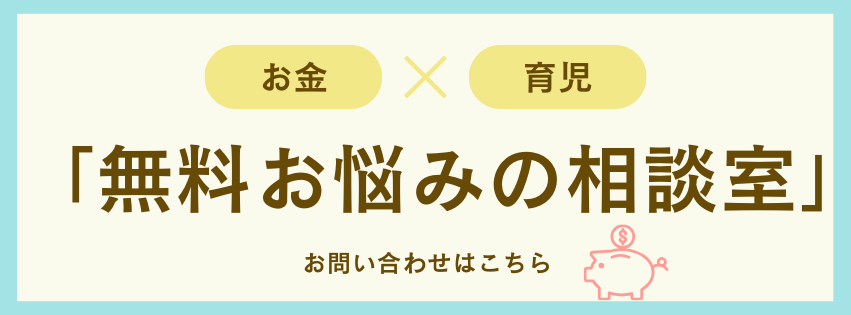
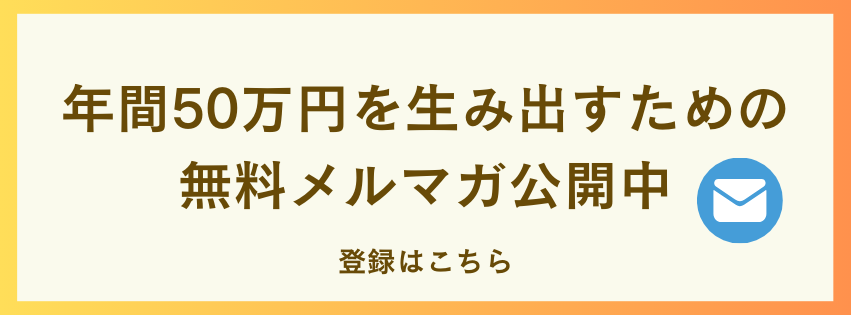
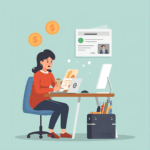


コメントフォーム